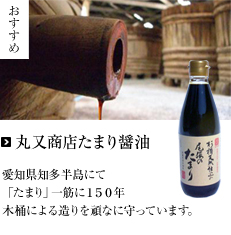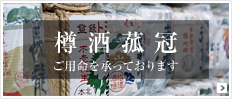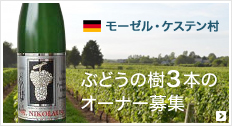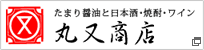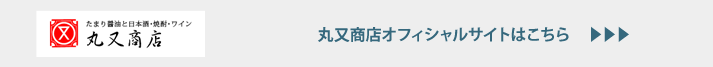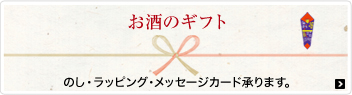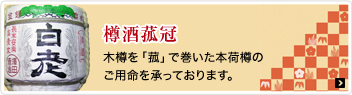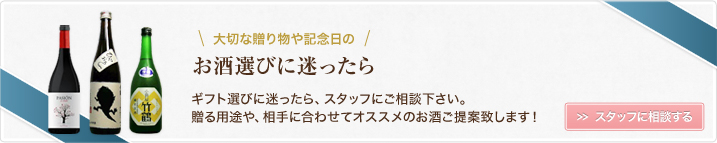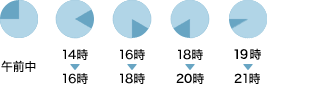茨城県大洗町の酒 月の井(つきのい) 和の月(なのつき)

茨城県は大洗に授かる酒!!

月の井のお酒をはじめて見た方は、その色味に驚かれるかもしれません。
無色透明ではなく、ほんのりとした山吹色や琥珀色。
それは素材の旨味が凝縮された複雑な味わいの色味です。
その酒は、他に類のないほど突出した緩衝力を誇ります。
緩衝力とは、味や刺激を和らげ、まとめる包容力のこと。
どんな料理もどんな飲み方も受けとめる懐の深さがあり、
体になじみ、飲み疲れを抑えるとされています。
だから毎日でも飲みたくなる。
素材がもつ本来の個性。
大洗の蔵にしか宿らない個性。
この瞬間にしか生まれない個性
それが月の井のお酒です。
<より自然な酒造り>

原料米の良さを十分に引き出したい
麹の力で米を溶かし、酵母による醗酵の勢いを大切にする
その為に、醪の温度コントロールを行いません。
毎日の変化を、そして大洗町の気候風土を感じながら
常温の蔵で醸しています。

有機栽培米を使って・・そして・・酵母無添加
生もと仕込みで醸す「和の月」
有機のお酒「和の月」このお酒は「なのつき」と読みます。
原料が有機米というだけでなく、酵母無添加の生もと造りで醸す伝統的なお酒です。
月の井創業140周年を記念して立ち上げたオーガニック日本酒「和の月」は、山崎正志氏が栽培し有機認定を受けた酒造好適米を使い、仕込む酒蔵は、熱湯と布できれいに拭きあげ、有機のお酒と称するための厳しい基準をクリアしてきました。
「ていねいな酒造り」をこだわりぬいてできあがった、洗米から仕上げまで昔ながらの手づくりのお酒です。
蔵元ホームページより

伝統的な日本酒ならではの趣を醸し出す
生もと仕込み
この江戸時代からの伝統的な製法をなぜやるのか
単なるノスタルジーではない
論語の温故知新という言葉にあるように古きを訪ねることで新しきを知る
伝統的な製法
伝統的な技術
伝統的な精神
きちんと継承していく事が逆に未来を切り拓いていくことになると考える
伝統とは普遍性があるもの
その時代しか通用しないものは伝統にはなり得ない
未來でも通用するのです、本当の伝統というものは
きちんと伝統を守る事は、実は後ろ向きではなく前向きなのだと・・
その上で、今の世の中に受け入れられるものとして表現されたお酒を造る
それが、普遍性のある伝統を活かした酒造りなのだと考えている
そして、アルコール度数が高いけれど
すっと喉を通って身体に馴染んでくる
ふわっと包まれるような感じ
舌先だけを喜ばせる酒ではなく
心と身体が喜ぶような酒




月の井酒造杜氏 石川 達也<Tatsuya Ishikawa>
「不射の射(ふしゃのしゃ)」とは

それは弓の名人の話から始まる
弓の道を究めようとする男が老子に卓越した技を披露した
老子から、それはまだまだだと言われる
それは、射の射だ
本当の境地とは「不射の射」だ
射(う)たずして射(う)つ
狙っている内はまだまだ
矢を放たずに的を捉える名人の境地「不射の射」
狙わない酒造り
こういう酒を造ってやろう
つまり、これはまだまだ
一生懸命造るにしても・・・


「狙わない酒造り」
こういうお酒を造りたい。
ゴールを設定して・・
これが、普通であり一般的です。
月の井酒造が行おうとしている酒造りは
この米がある、この水がある、大洗の気候風土ってこういうものだよ。
自分達が持っているものを積み重ねて結果出来るお酒なんですね。
酒造りのベクトルが違う。
結果だけを追い求めない。
つまり、狙わない酒造り。
<月の井酒造談>
(お知らせ)
2024年にNHKで放送されたものから文字起こしを行い、月の井酒造さんに許可確認をしてから載せています。
つまり、NHKからもこの放送された内容を大いに活用してくださいとのことです。という確認です。
清酒「月の井・和の月」醸造元
株式会社月の井酒造店
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜638